|
「その、だから、赤い花なんです」 何やら話し合っているらしい大きな声が聞こえてくるのはその街の花屋からです。 「どうかしたんスか?」 困っているらしい、帽子をかぶった男の後ろから赤也は声をかけてみました。 |
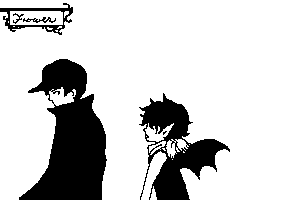 |
|
「手伝いましょうか?」
(買わなければいけないような、気が) ――クリスマスといっても何をあげたらいいのか思いつかないから、と言ってな。 (もしかして) 「それって、あれじゃないッスか?」 |
 |
|
「そうだ、これだ!」
「お前のおかげで買うことができた。礼をしよう」 |
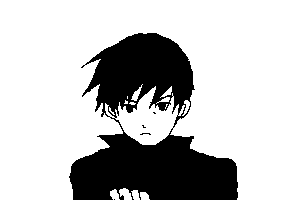 |
|
「仕方がないな、これでどうだ」
|
 |
|
男がかぶせてくれた帽子はぶかぶかでした。 赤也はなんだか、泣きたいような気持ちになりました。
男の名前は真田弦一郎。 |